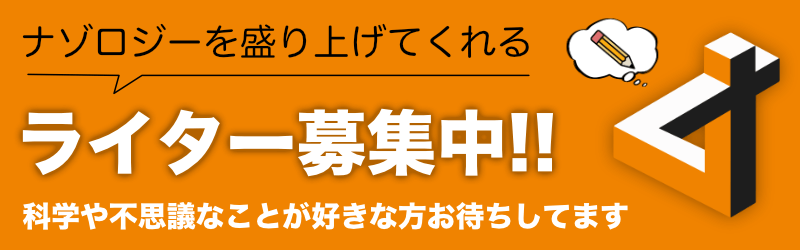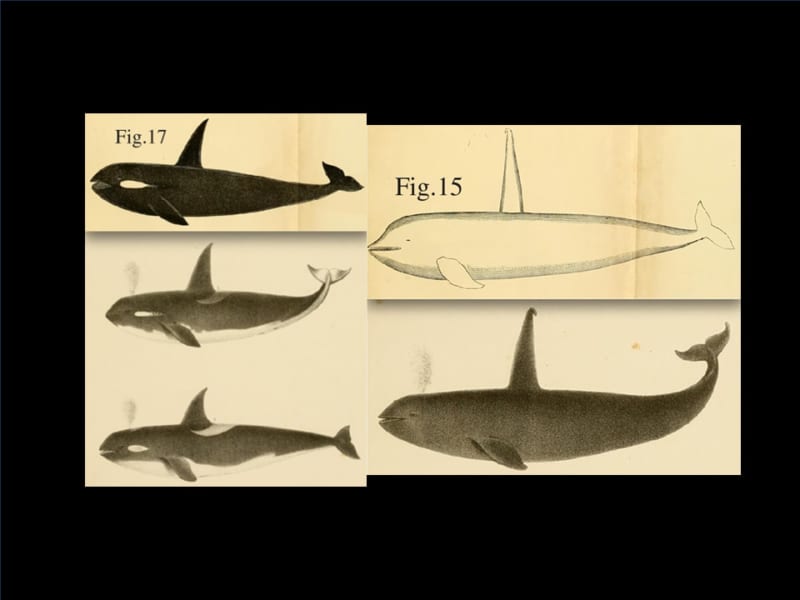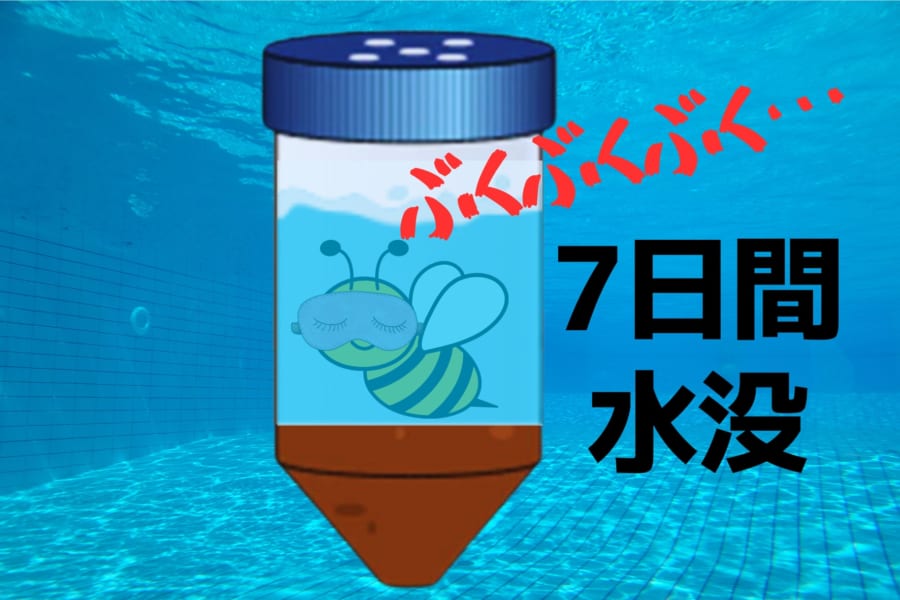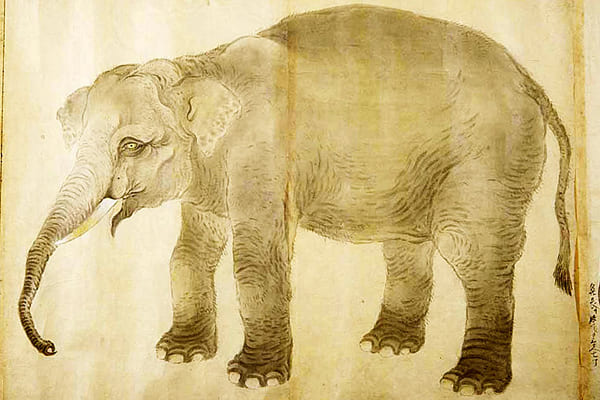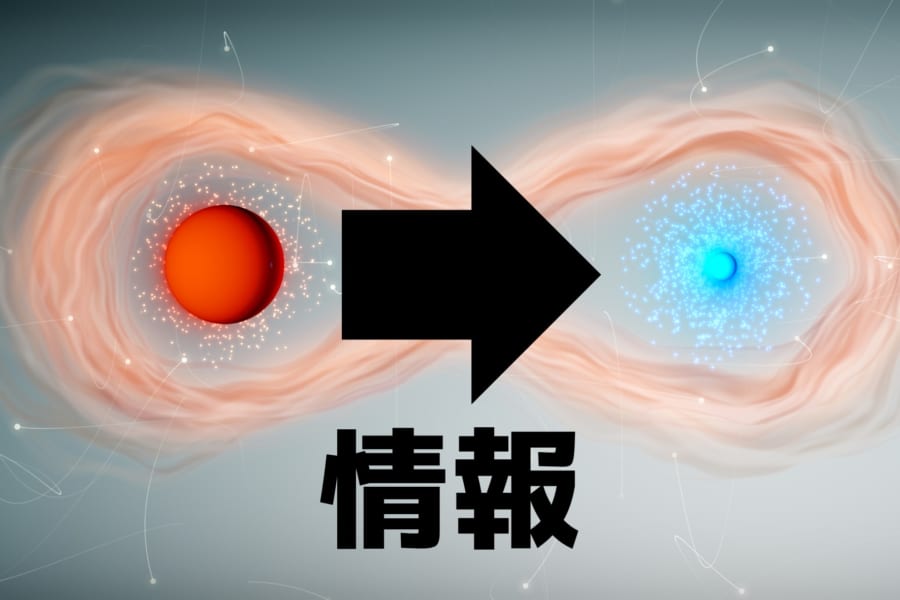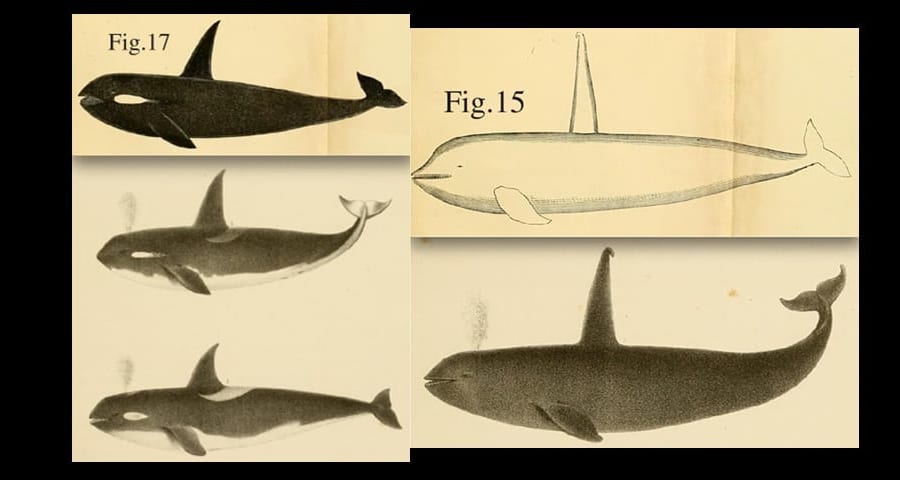ダッカ・モスリンが伝説である理由

ダッカ・モスリンはなぜ姿を消したのでしょうか?
それは、誰もその織り方を知らないからです。
またダッカ・モスリンに使用される綿花は、「Phuti karpas」という名の種であり、現在ではそれがどんな植物だったか正確には誰も知りません。
これは世界の綿花の90%を占める「Gossypium hirsutum」とは全く異なっていたようです。
Phuti karpasは気まぐれで、糸にしようとするとすぐに切れてしまうとのこと。
またGossypium hirsutumの細長い綿糸に比べて、Phuti karpasの綿糸はゴツゴツとしていてほつれやすいとも言われています。
Phuti karpasは工業機械による安価な綿布には不向きですが、ダッカの人々はその歴史の中でPhuti karpasを使いこなす独自技術を発展させました。

その16の工程の中には、「地元に生息する人食い魚の独特な歯で綿をきれいに整える」「短い綿繊維を伸ばすのに高い湿度が要求されるため、1日で最も湿度の高い早朝と午後遅くに若い熟練者が作業を行う(高齢者は細い糸が見えないため高い技術で扱えない)」などが含まれていました。
ちなみに、1kgのPhuti karpas綿から、たった8gのダッカ・モスリンしか作れないため、非常に手間と費用の掛かる作業だったと言えます。
またダッカ・モスリンの最大の特徴と言えるのが、糸の数です。
現在作られているモスリン(平織り)の糸の数は40~80本です。ところが、ダッカ・モスリンの糸の数は800~1200本です。現在の綿織物と比べても桁違いに多いのです。
一般的に、糸の数が多ければ多いほど生地は柔らかくなり、良い状態を保ちやすいと言われています。
そのため、糸の数だけでもダッカ・モスリンがいかに高品質の織物だったか分かるでしょう。