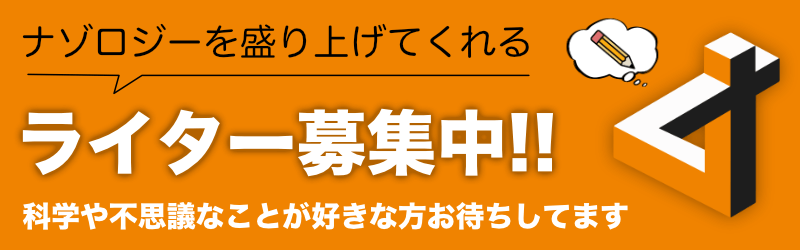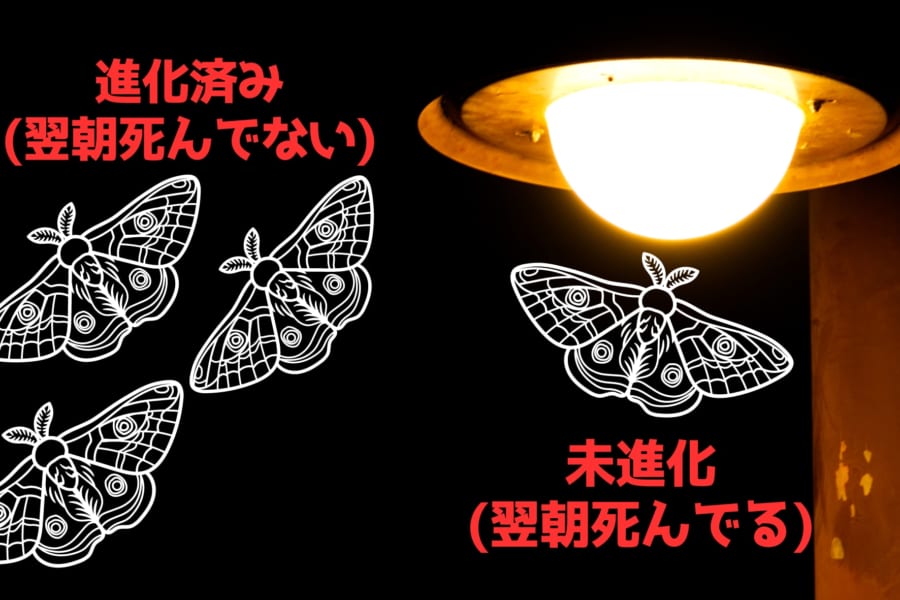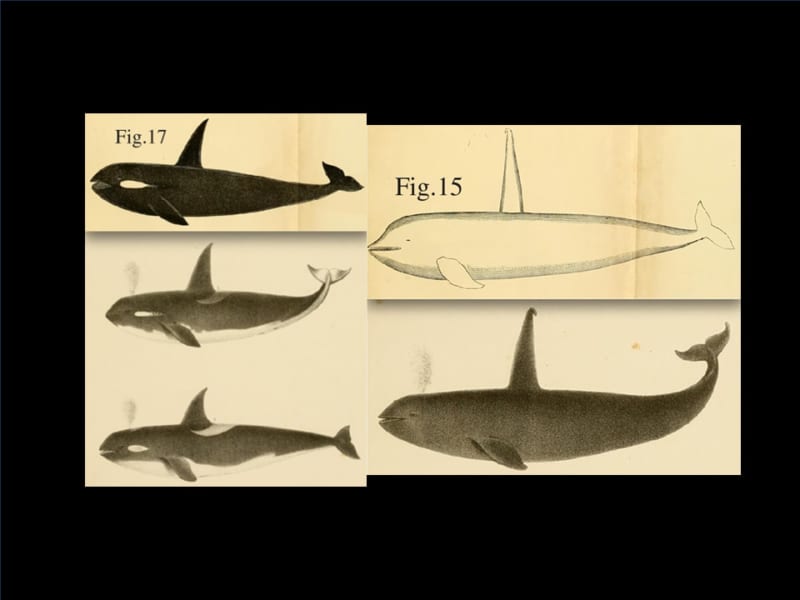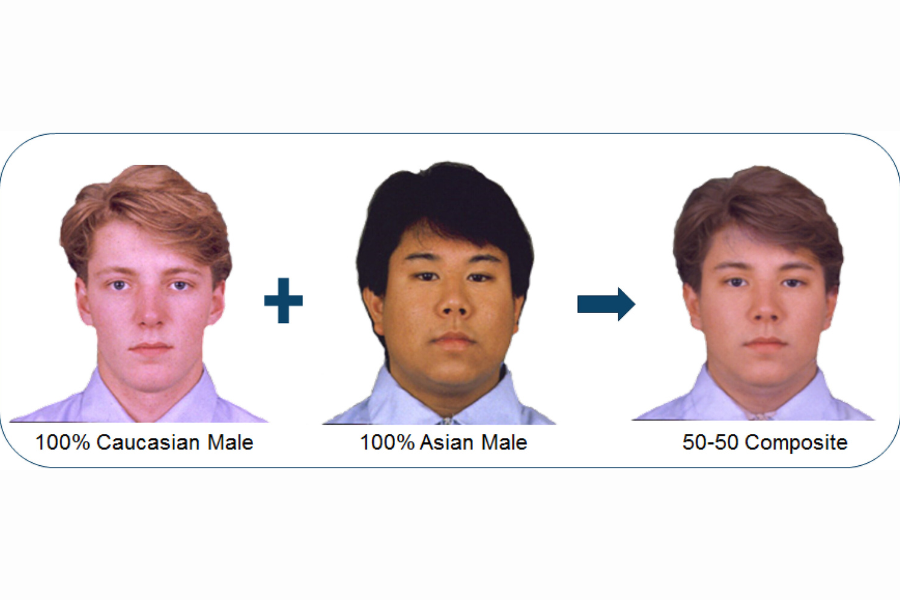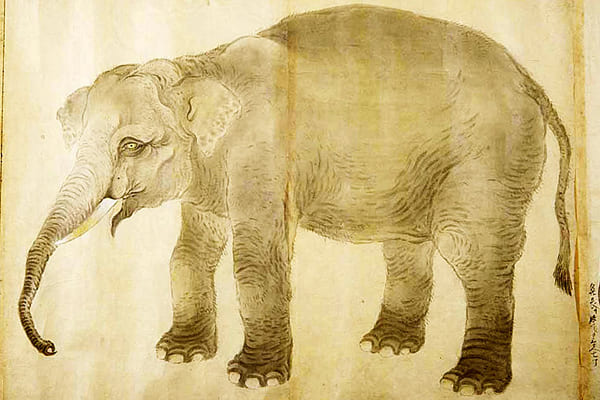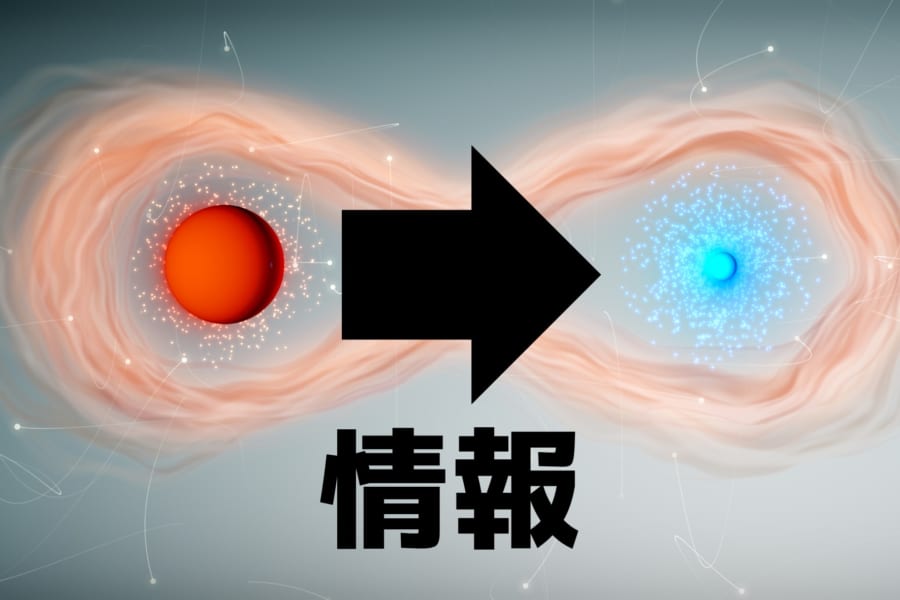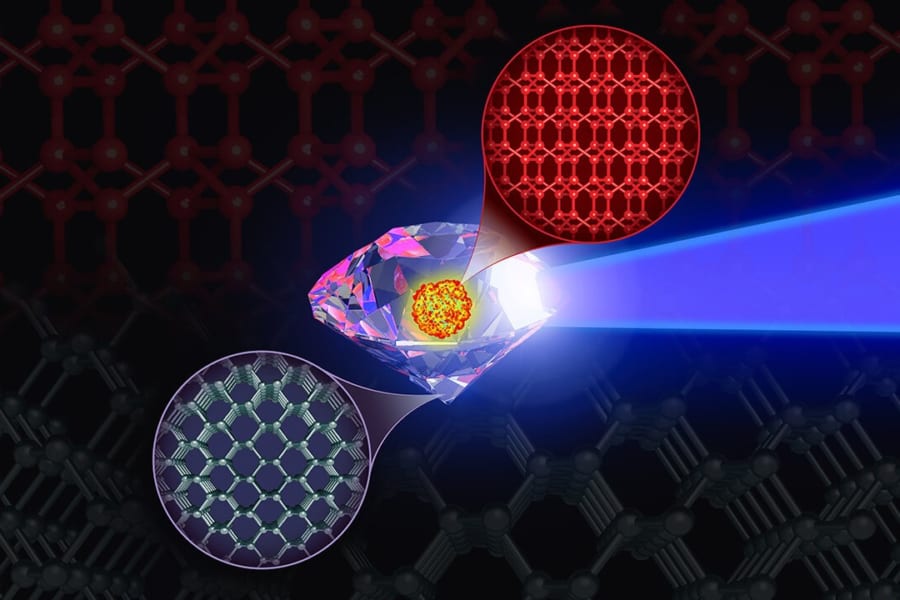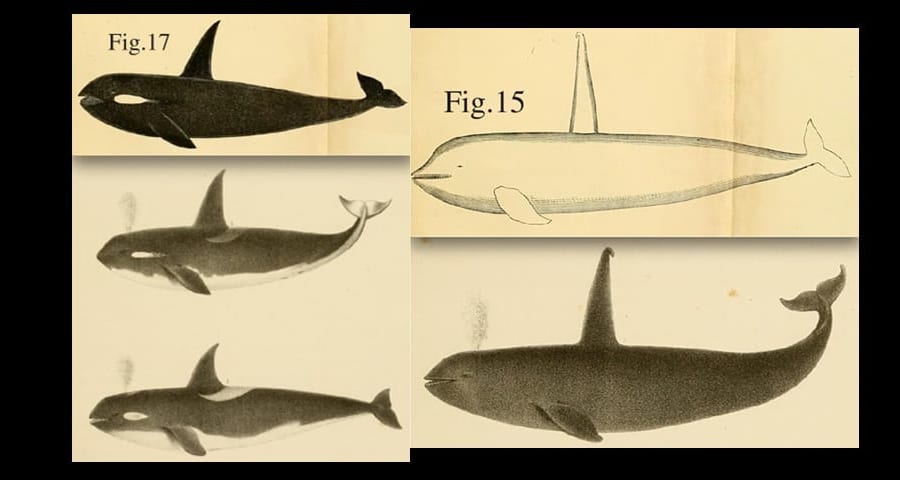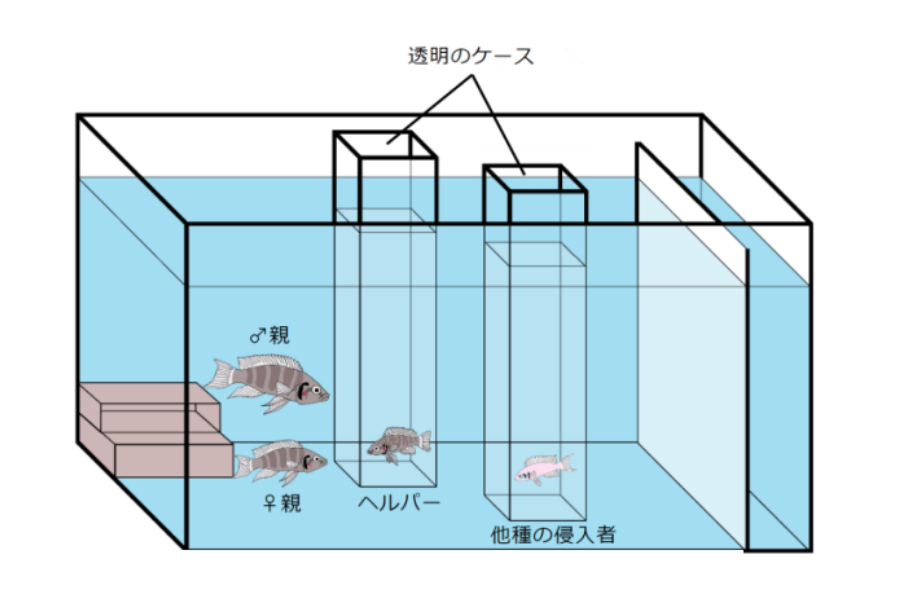鳥の血液は「暖房システム」として機能していた
寒さの厳しい冬になると、動物たちは各々のやり方で暖をとります。
地中で冬眠したり、洞窟の奥深くに隠れるもの、あるいはミツバチのように巣の中に群がったり、蝶のように暖かい土地に移動したりするものまで様々です。
とりわけ寒さに弱い生き物は私たちヒトでしょう(冬時期に布団から出る時の苦しみを思い出してみてください)。
しかし、これらの生き物とは対象的に、鳥は冬でも元気に空を飛びまわり、川面を泳ぐものまでいます。
この偉業を可能にしているのは、赤血球にエネルギー工場である「ミトコンドリア」を含んでいるからです。
哺乳類以外の脊椎動物は、赤血球にミトコンドリアを持ちますが、そのミトコンドリアには熱を生産する能力があります。この熱生産が、鳥が冬でも外を飛び回れる理由と関係している可能性がありました。

そこで研究チームは、鳥類におけるミトコンドリアの機能を解明するため、シジュウカラ、ヒガラ、アオガラというスズメ目の鳥を対象に、「初秋」と「晩冬」の2つの季節に分けて調査を開始。
採取した血液サンプルから赤血球を分離し、ミトコンドリアの酸素消費量を測定できる高感度機器「レスピロメーター」を用いて、エネルギーの生産と熱の生成に費やされた酸素量をそれぞれ測定しました。
その結果、冬に採取した血液の方が秋口より多くの酸素を消費しており、さらに、ミトコンドリアの熱生産量が増えていることが判明したのです。
研究主任のアンドレアス・ノール氏は「鳥類は冬になると代謝が活発になり、多くのエネルギーを必要とします。
ところが、冬時期のミトコンドリアはエネルギーよりも熱の生成を優先していたのです。
鳥が血液を暖房システムとして調節できるとは考えてもみなかったので、非常に驚くべき結果となりました」と述べています。

また、鳥が暖をとる方法はこれだけではありません。
例えば、多くの鳥は、大きな胸の筋肉を振動させることで熱を発生させ、体温を高めます。
これにより、体重が半オンス(約15グラム)にも満たないアメリカコガラのような鳥でも、外気温が0℃以下の中で、体温を37.7℃に保つことができるのです。
それから、羽毛の間に暖かい空気を保持したり、片足立ちによって保温効果を高める鳥などもいます。
一方で、こうしたユニークな行動にはまだまだ謎も多く、チームは、冬の寒さと血液の暖房機能との関連性も含めて調査を進める予定です。
その中で、冬に鳥たちが食べるエサが、ミトコンドリアの生成と利用にどのような役割を果たしているのかも一つの焦点となります。
記事内容に一部誤りがあったため、修正して再送しております。