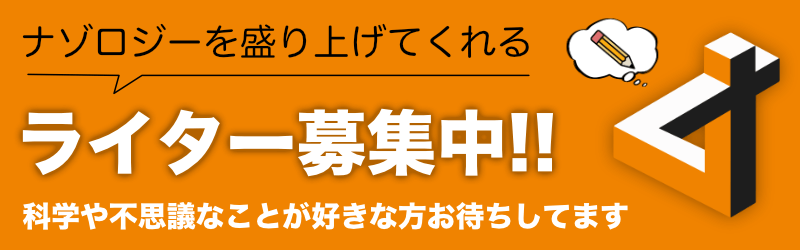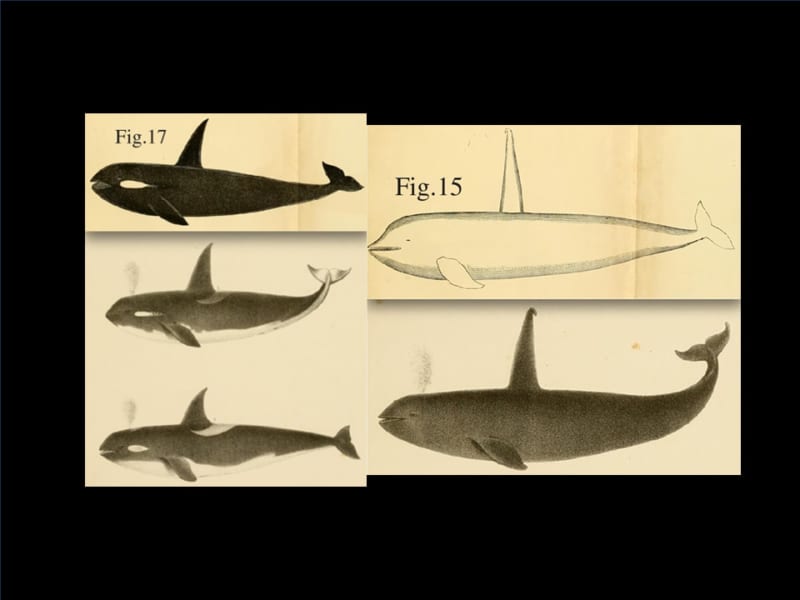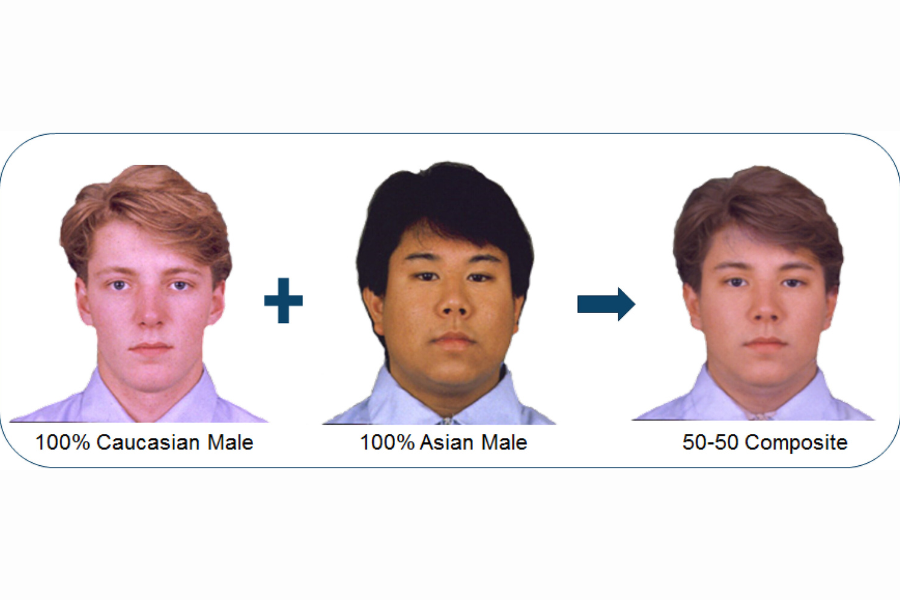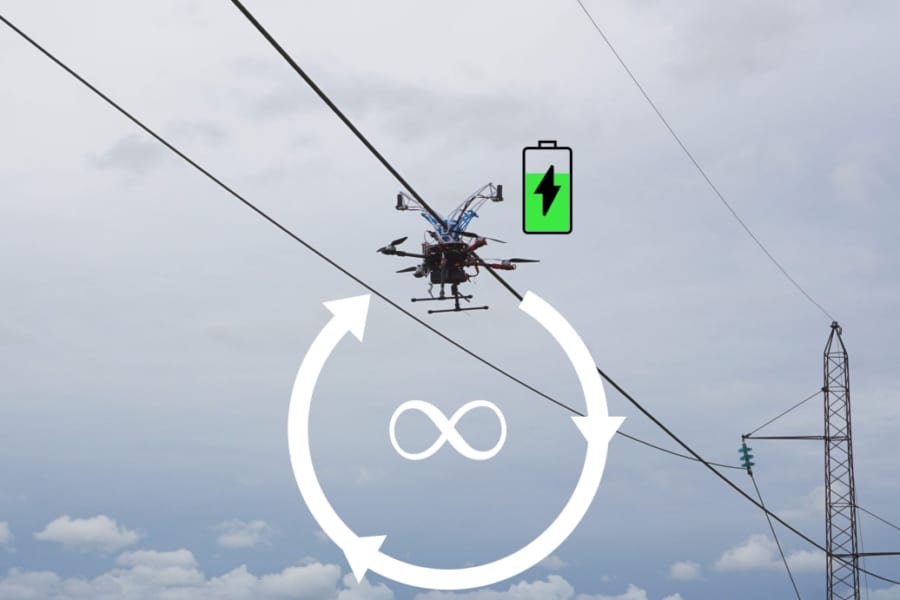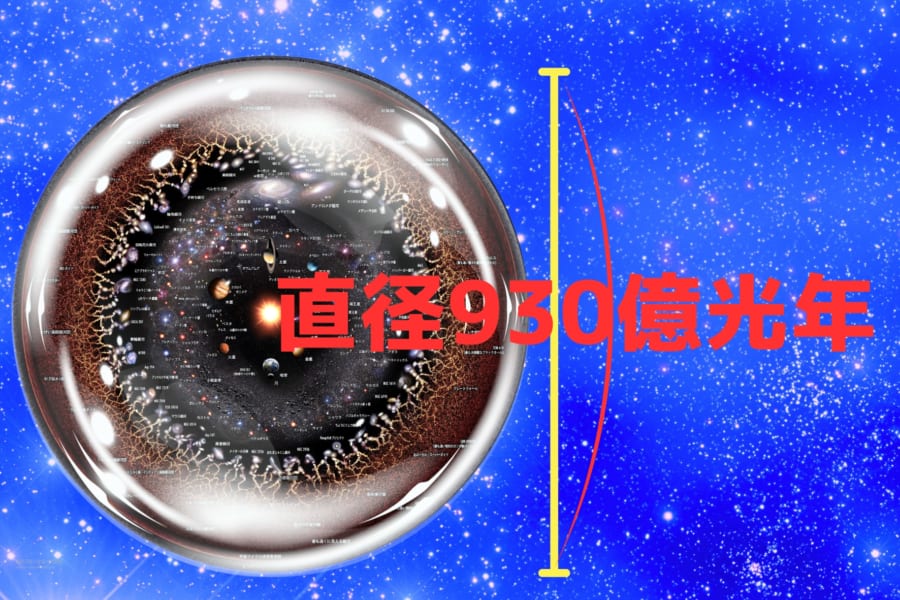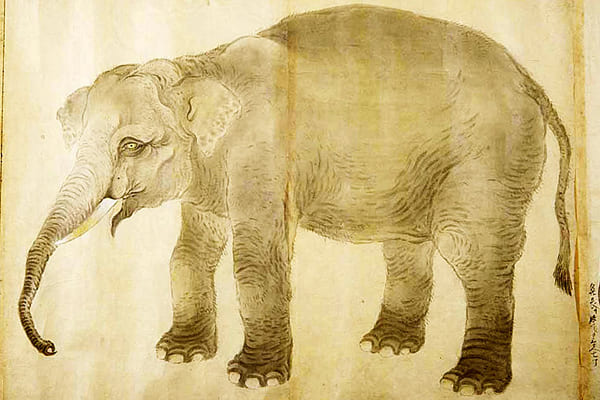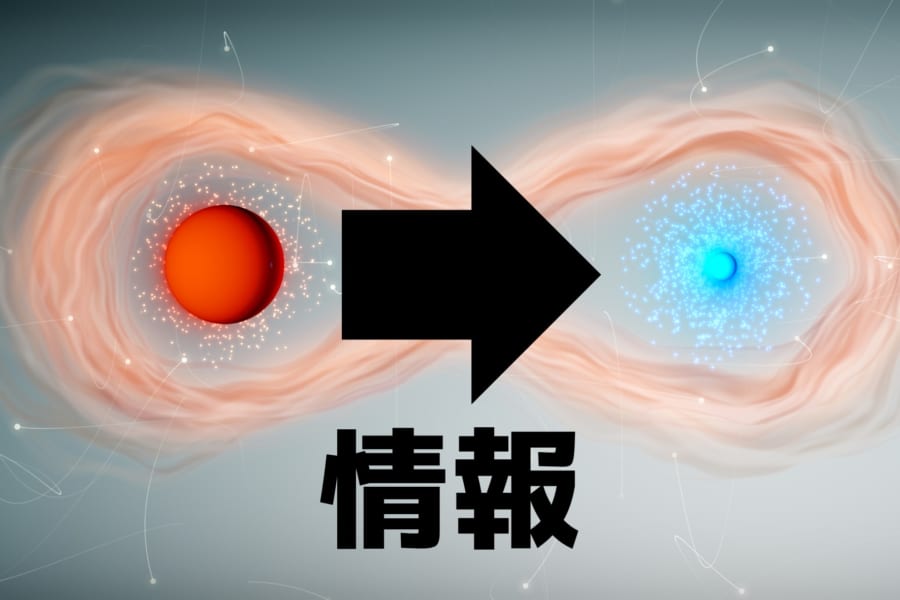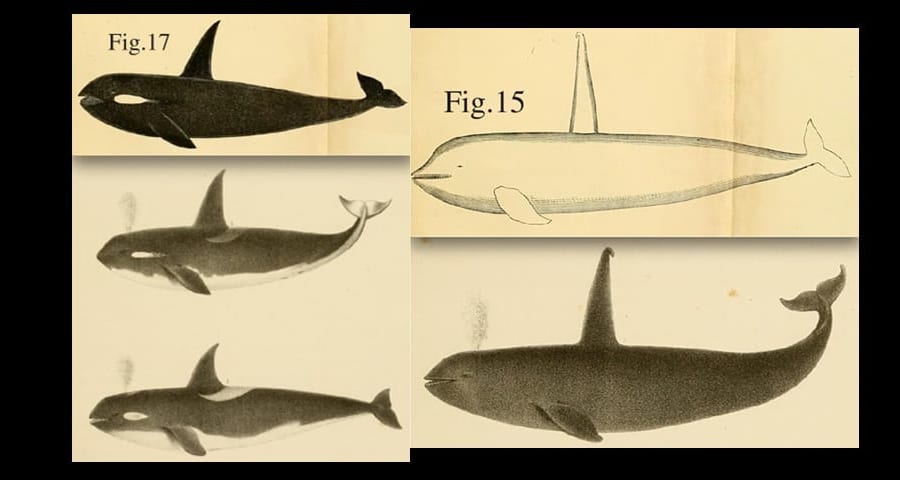孤立したハエだけ「過食&寝不足」になる
ショウジョウバエは社会的な生き物です。
グループでエサを食べ、交尾前の儀式で相手にアピールし、個体間でのケンカも頻発します。
彼らの睡眠時間は、実に1日16時間におよび、昼間のゆったりとした仮眠と夜のしっかりした休息の2つに分かれています。
本研究では、社会的なショウジョウバエが、集団から隔離されることで、どのような変化を起こすかを調べました。
研究チームは、最初に、ハエを個体数の異なるグループに分けて、行動に違いがあるか7日間にわたり観察。
その結果、多くの集団で生活したハエには何の変化もなく、また、2匹だけ隔離したハエも満足そうでした。
ところが、1匹だけを完全に隔離したところ、ほかのハエたちと比べて、食事量が増加し、睡眠時間が減っていたのです。
その個体の脳を調べてみると、「P2ニューロン」と呼ばれる小さな脳細胞グループが、睡眠と摂食行動の変化に関与していることを特定しました。
実験的に、孤立したハエのP2ニューロンを遮断したところ、過食が抑制され、睡眠時間も回復しています。
一方で、1日だけ隔離したハエのP2ニューロンを活性化させると、まるで1週間ずっと独りぼっちだったかのように、過食と睡眠不足が引き起こされました。
P2ニューロンは、孤立した期間や孤独感の強さの認識にかかわっているようです。

さらにチームは、これらの観察結果を詳細に検証しました。
不眠症のハエを人工的に作成したところ、睡眠不足だけでは過食が起きないことが確認されています。
また、P2ニューロンを操作するだけで、隔離されていない集団内のハエも過食や睡眠不足を起こすかを実験。
その結果、ハエの行動に変化は見られず、過食と睡眠不足を起こすには、短期間だけでも実際に隔離することが必要と判明しました。
ハエから人間に至るまで、多くの社会的動物は、孤立すると食べる量が増え、睡眠時間が短くなります。
その理由は定かでありませんが、研究主任のマイケル・ヤング氏は「社会的な孤立は、将来に対する不確実性を示す」と指摘。
「困難な状況に備えるためには、できるだけ多くの時間目を覚ましておき、食べ物があればいつでも食べるようにすることが必要なのかもしれない」と続けます。

今回の研究だけでは、ロックダウン中の人間が、孤立したハエと同じ生物学的メカニズムで、過食と寝不足を起こしているかは判断できません。
しかし、ハエの孤独感に反応するニューロンは特定されたので、今後、人を含む社会的動物を対象に、隔離と過食・寝不足の対応関係を探ることが可能でしょう。
ヤング氏は「臨床的な研究によると、アメリカの多くの成人が、コロナ感染による隔離措置を受けた1年間で、体重の大幅な増加と睡眠不足を経験していることが分かっている」と言います。
やはり、双方の関係には、生物学的なメカニズムが隠されているのでしょう。