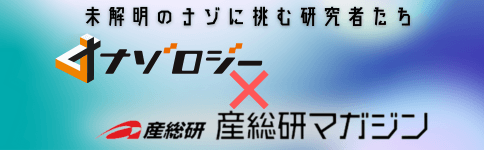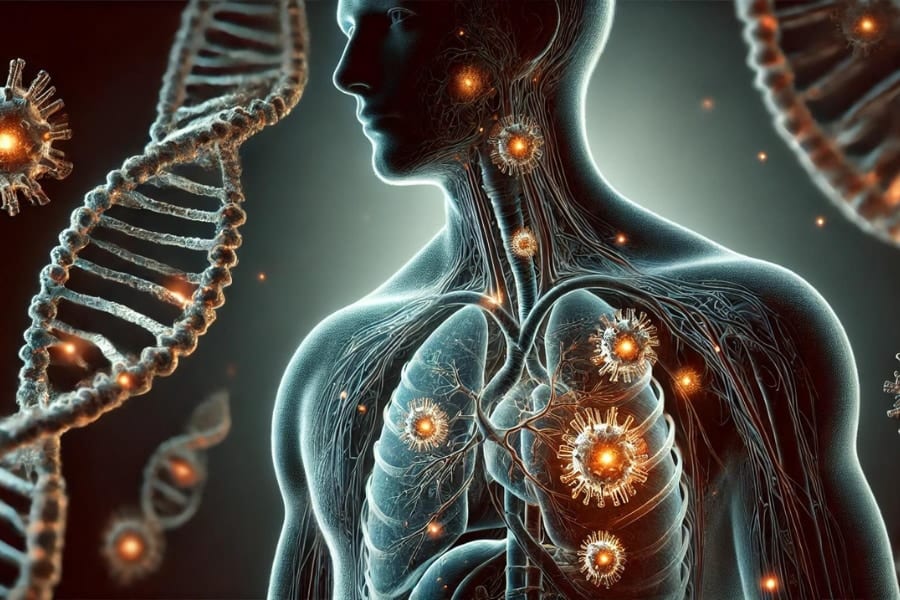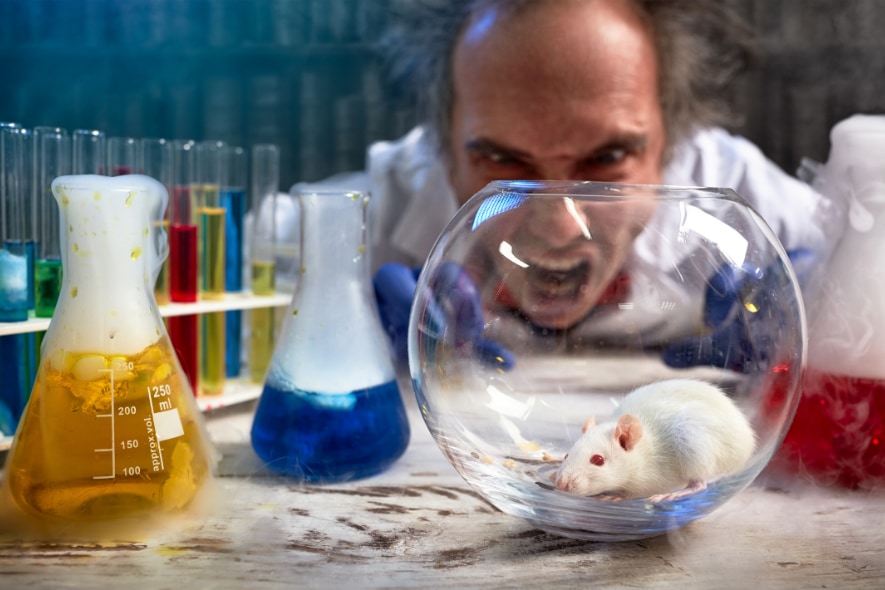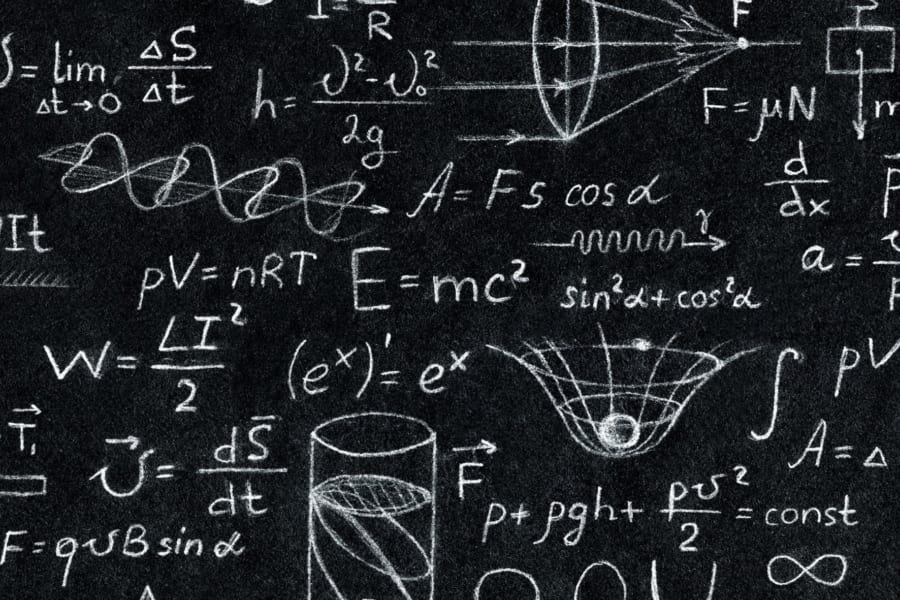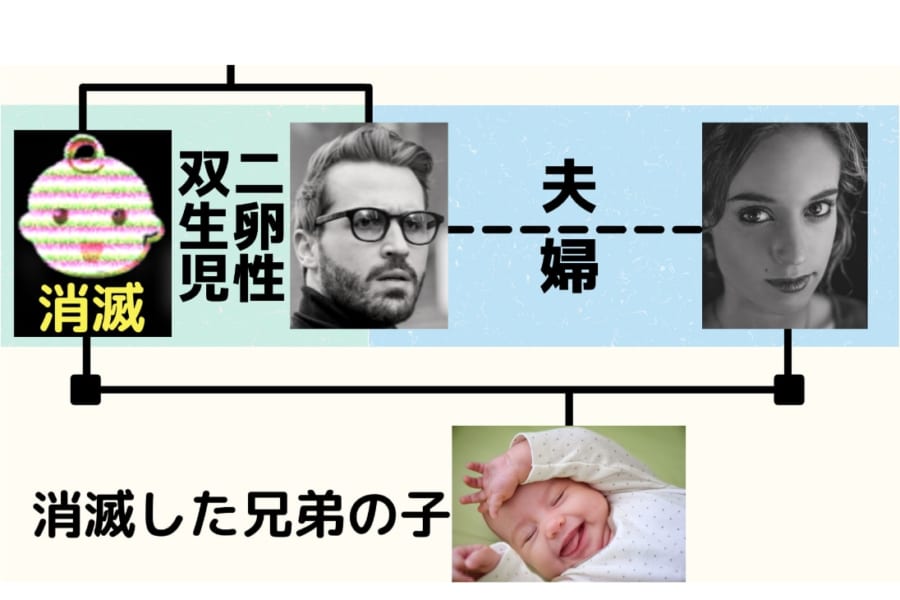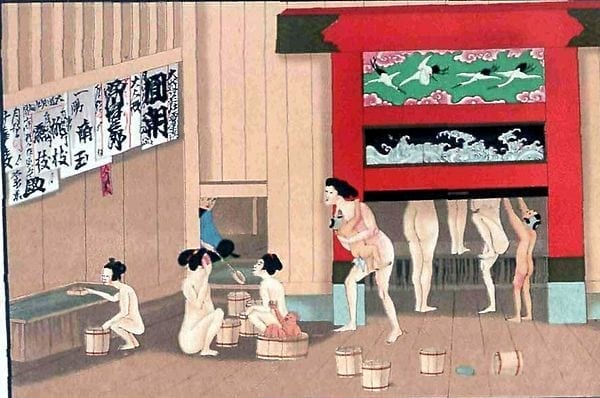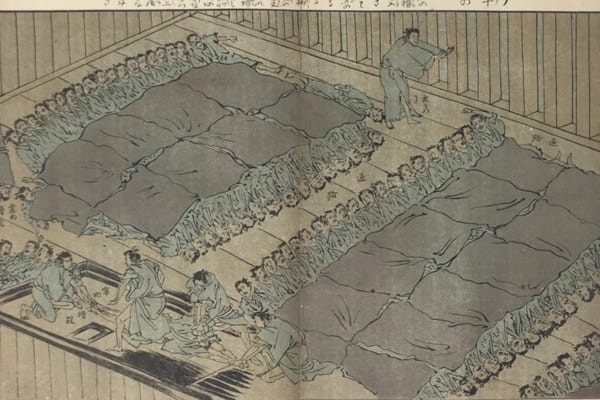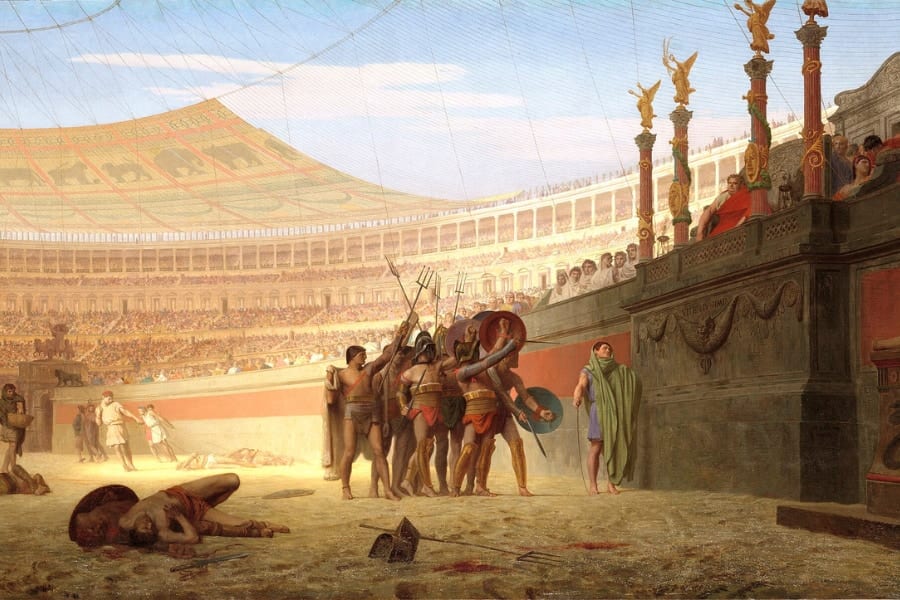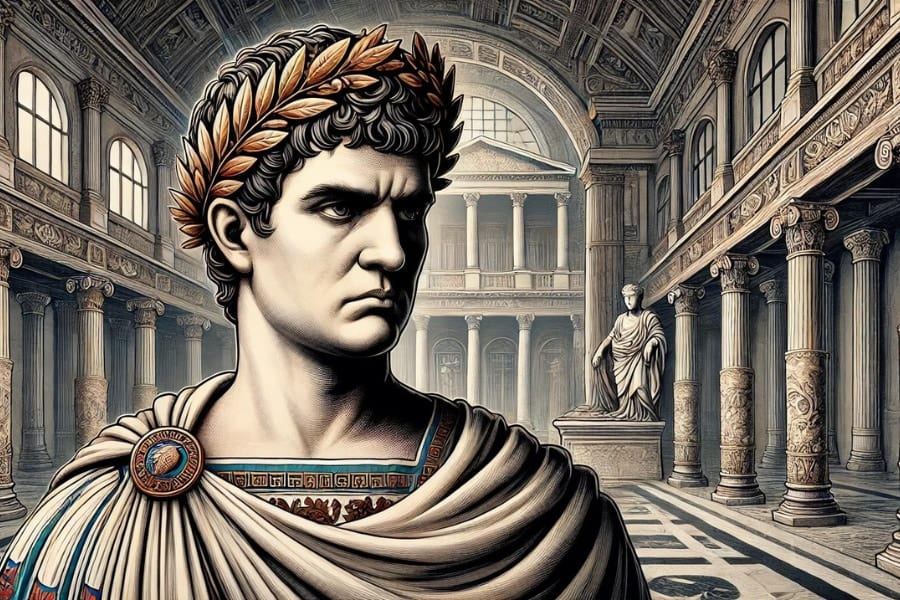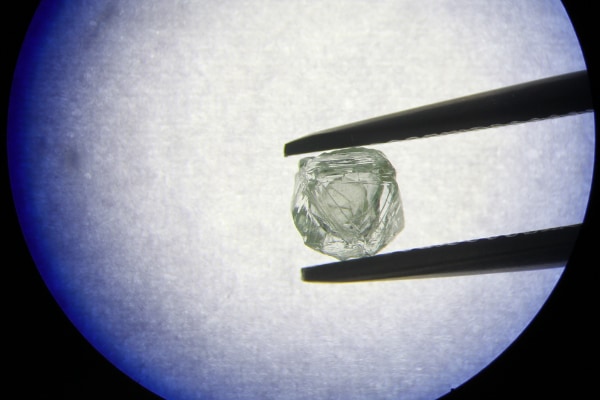主食の多様化がすすめられた戦争初期
日中戦争が起こった1937年当時では、統治下の朝鮮や台湾で米を増産させていたこともあり、米不足はあまり問題になっていませんでした。
しかし1939年に朝鮮で空前の旱魃が起こると、米不足が問題になってきたのです。
通常時であれば海外から米を輸入して賄うという手段が取られますが、先述したようにその時は中国と戦争中であり、輸送力を割く余裕はありません。
この状況下で、米を節約するために、混食と代用食が奨励されるようになったのです。
混食は、米に他の具材を混ぜて調理する方法であり、当時の主な具材は芋類や豆類、穀類などでした。
これだけ聞くと現在の混ぜご飯と大して変わらないように見えますが、通常の混ぜご飯では全体の4分の1程度である具材の比率が半分近くになるなど、混食では美味しさよりもカロリーの摂取が優先されていたのです。
一方、代用食は米の代わりに別の主食を食べるというものであり、パンやうどん、芋などが広く利用されました。

また女性向け雑誌では、ホットケーキ、お好み焼きなどの粉物料理が紹介され、この時期から食文化の変化が起きていることが見受けられます。
現在ではパンや麺類を主食にしているも多いですが、当時は米が主食として絶対的な地位を占めており、それゆえパンやうどんが代用食という文脈で推奨されることとなりました。
こうした代用食の動きは世間に広まっていき、デパートの食堂に芋の握り寿司などといった米なしメニューが出されたりしたのです。
また米の節約だけではなく、米を白米ではなく玄米にする動きも進んでいきました。
玄米は、稲の果実である籾(もみ)から籾殻(もみがら)を除去しただけの米であり、糠や胚芽などといったものが取り除かれていません。
それ故白米と比べて栄養が豊富であり、食糧難の時勢において非常に好まれていたのです。
玄米食については当時の首相の東条英機が玄米を常食としていたこともあり、先述した混食や代用食と比べて、玄米食の推進は国民の理解を得ていました。